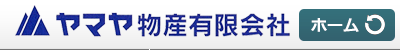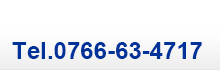給水車が回ってくる。それを受けるポリタンクがあればひとまず安心。 と思っている方が大半ではないでしょうか?意外と水は手元に「ただ」あるだけでは使えません。普段から水道のように使っているのであれば、水道のように使えなければ意味がありません。 そこでヤマヤが避難所に必ず持っていくものとして「受水槽付ポンプ」があります。水を入れて水道にする装置です。 これを使えば流し台でも手洗いでも後片付けでもなんでも使えます。普段慣れない数百人~数千人クラスの調理をするのに、ポリタンクで手を洗うなんていうのは、非現実的すぎるとは思いませんか?
トピックス
北海道胆振東部地震 新聞掲載
北海道胆振東部地震からヤマヤ部隊が戻ってきて二日目、地元紙で記事が掲載された。炊き出しを一番乗りするという感覚は社長独自の考え方。しかし、その考え方には非常に賛同する。トイレが早く設置されなければいけないというのが世情ではあるが、それと同時並行で炊き出しも実施される必要があると思う。北海道厚真町にも「食材は大量にある」が「大量調理する器材がない」この問題は阪神淡路大震災からずっと課題になっていることだ。商売だから、言っているのではない。避難所には炊き出し器が必要なのだ。 今後も変わらず、この思いは伝え続けていきたい。
北海道胆振東部地震 レポート
本日、ヤマヤ救援部隊が北海道厚真町から戻ってきた。 厚真町役場裏にある福祉センターで一食2000の数量を炊き出ししてきた。 今回は北海道営業の最中だったため、自衛隊より早く現地についた。 現地はさすが北海道、食材は豊富にあったが、大量に炊き出しする機械は存在しなかった。 そこを拠点に2000食。 今まで関わってきた震災の経験を基に、直炊飯による炊き出しを行った。
まかないくん解体新書⑦「LPガスバーナー、設置の時、着火の時」
こんにちは!まかないくんです。 「炊き出し器なんてみたことないから、何が違うのか分からない」 という意見にお応えすべく設けました、この企画。 「まかないくん解体新書2018」 栄えある第七回のテーマは「LPガスバーナー、設置の時、着火の時」 さて、皆さん。 まかないくん解体新書をここまで読み進められた方ならば、カマドについていろいろな知識が身についてきたのではないでしょうか? カマドの歴史を辿っていくと、一番最初は「薪」で使われており、後に「ガス」、最後には「電気」となっており、カマド・・・つまり現代で言うところの「炊飯ジャー」は電気式になっています。 しかし、炊き出しに使われるカマドは「薪」「ガス」が主流でした。 そのため、世にある炊き出し器を見ると、ほとんどがガスのタイプであり、その作りも非常に似通っています。 その中でまかないくんがこだわったのは、「設置の仕方の簡略化」と「ミス着火確認の簡略化」です。 <焚口の欠き込みがわかる絵> まかないくんの焚口(薪やバーナーを入れる口)の形状です。矢印のところにある窪み。 この窪みは実はLPガスバーナーの足が固定できる窪みなのです。 LPガスバーナーの使い方 こうすることで、今までのカマドではなかなか難しいとされてきた「バーナーの炎を鍋の中心に持っていくこと」を誰でも簡単にできるようになりました。 そして、もう一つの特色が「ミス着火確認の簡略化」です。 着火したかどうかを確認するとき、どうしても屈んで覗き込まないといけません。 しかしその体制が非常に苦しい体勢だとの要望から、上からのぞき込むことで着火状態を確認できるように反射鏡をつけてあります。 特に、炊き出し器を使用される方々は若い人とは限らず、年配の方々から「屈んで覗き込む体勢が厳しくて」と言われたのを思い出します。 特にまかないくんもぎっくり腰をはじめ様々な腰の病を持ちはじめてから、その気持ちがよくわかるようになりました。 何気ない使用者さんたちの言葉。 その言葉を受けて反映しての繰り返しでまかないくんは今の形に近づいていきます。
まかないくん解体新書⑥「灯油バーナーのダンパー調整」
こんにちは!まかないくんです。 「炊き出し器なんてみたことないから、何が違うのか分からない」 という意見にお応えすべく設けました、この企画。 「まかないくん解体新書2018」 栄えある第六回のテーマは「灯油バーナーのダンパー調整」 まかないくんの最大の特色といってもよい「灯油バーナー」について説明ます。 ヤマヤ物産(有)製で発売して3年目から着手、これまで18年をかけて試行錯誤を繰り返しております。 今も2か月に一度は実験による数値の把握を行っていますので、お客様へ出荷されるまかないくんは数値的にも安全な商品になっております。 Hi/Loの二段式燃焼のため、通常であればダンパーの調整が必要です。 HiとLoで出力が100:30の設計になりますが、その出力に応じてダンパーの調整をしなくてよいように製造しています。 ダンパー調整をお客様に委ねることは、大変危険だと当社では考えております。 本来、ダンパーを絞らなければならないところで開いたり、開くべきところで閉じたりすると、一酸化炭素が大量に発生してしまうことになりかねません。 そうなった場合、お客様責任という言い逃れもできるかもしれませんが、ヤマヤとしては安全にお使いいただけるようにダンパー調整を行わずにHiLoをお使いいただけるよう、独自の機構でダンパー調整を行っています。 そのため、スイッチのHiLoを切り替えていただくだけで最適なダンパー調整を行うことができ、誰でも快適にお使いいただける「灯油バーナー」になっています。 ヤマヤの技術の集大成である「灯油バーナー」お使いになられてみませんか?
まかないくん解体新書⑤「煙を消す」
こんにちは!まかないくんです。 「炊き出し器なんてみたことないから、何が違うのか分からない」 という意見にお応えすべく設けました、この企画。 「まかないくん解体新書2018」 栄えある第五回のテーマは「煙を消す」 まかないくん自身、薪で使用することが「一番難しい」と感じています。 なぜか?以下の図のようになるからです。 LPガスバーナー・灯油バーナーであれば熱方向が一定ですが、 ※大変見苦しい画像で申し訳ございません。 薪になると、熱方向が分散し、四方八方に熱が行くからです。 薪炊きによる断熱構造で下には熱が行かなくなりましたが、側面は一重のため熱が行ってしまう。 そこで二重構造にすることにしました。 そこで、当時流行っていた「薪ストーブ」の「ツイスト燃焼」という技術を採用しました。 その形状のために、側面を今までアルミ缶のように一重ではなく、「魔法瓶」のように二重構造にしました。 狙いとしては以下のような排気ルートを確保したかったからです。 そうすると内部の温度が上がり、高温域を排気が通るため「完全燃焼して排気」されるため、煙が消えました。 そして煙が消えると同時に、中の薪も「薪→炭→灰」と段階を踏んで燃え尽きるため、灰の量が少なく、燃え残りの炭も極端に少なくなりました。 これはカマドの中の温度の高温状態が続き、しっかりと完全に薪が蒸発した状態で燃え尽きたことを意味しており、そのおかげで薪使用の場合、少量の薪で長時間使用が可能になりました。 薪炊き用で優秀なカマドになった「まかないくん」ですが、ここで問題が発生しました。 それは・・・次回をお楽しみに。
まかないくん解体新書④「まかないくんの底っ、こだわりなのっ!」
こんにちは!まかないくんです。 「炊き出し器なんてみたことないから、何が違うのか分からない」 という意見にお応えすべく設けました、この企画。 「まかないくん解体新書2018」 栄えある第四回のテーマは「まかないくんの底っこだわりなのっ」 これまで2回・3回を通して底面は「3層構造」であれば長期的にキャスターが劣化しないことがわかりました。 そして幕間でお話した戦場での炊飯のやり方を参考にし、以下のような形状にしました。 これにより以下のメリットが得られます。 キャスターが熱によって劣化しない 灰が下にまとまって落ちる。 薪が真ん中に寄るため、火バサミなどで薪を移動せずに燃やすことが出来る。 これで「動かせる」が完成しました。 ヤマヤ物産で提供するすべてのカマドの底形状は、この形状で統一しています。 実はこの形状のおかげで、大変評価を受けたことがあります。 それは「東日本大震災」でした。 あの震災は「地震」というよりも「津波」の災害。 津波が引いたあとも、避難所では満潮の時には屋外は水浸しになるところもありました。 つまり、以下のような使い方もされてしまう可能性がある震災でした。 それぞれ、取扱説明書には禁止されている使い方ではあります。 しかし、災害時、「どうしても使わなければならない場面で使える商品こそが防災用の炊き出し器ではないでしょうか?」と私たちは考えます。 普段であれば確かに危険な使い方として注意します。 しかし、いざまさかになったとき、安全性の面において「過剰」であるほどの性能を確保しておくことが大事だとヤマヤは考えます。 その一端である、「底形状」。 ご理解いただけると幸いです。
日本キャンプ協会「CAMPING184」にて掲載
お袋のワザを掲載いただきました。 CAMPING第184号の11pに紹介いただいてます。 ご覧になってください。
幕間:野外炊飯の方法
こんにちは!まかないくんです。 本日は解体新書から少し外れた幕間をお知らせしたいです。 その名も「野外炊飯の方法」です。 かつての戦場にて、炊飯を行う場合、実際にはこうなっていたというお話です。 ※相変わらず見苦しい絵ですが、土の線を表しています。 この土を以下のように、 真ん中に窪みができるように、掘り込みます。 そして、そこに目皿を乗せ、 その上にドラム缶式を乗せます。 そして中に薪を入れて火をつけることで、 下の掘りこんだ隙間から空気が入り、良く燃えます。 そして、薪をどんどん追加していくと灰がたまりますが この形状であれば下の掘りこんだスペースに灰がたまり、 燃焼の邪魔をすることがありません。 当時はこのような手間をかけて使用していたそうです。 今の私たちの身の回りには、なかなか土のところがなく、炊き出しをするときに 掘りこむスコップ等も手間もかけることはしません。 ということは、カマドの形状は この形では不十分で、 この形が本来ではないかと考えました。 いかがでしょう皆さん。 こちらの方が合理的な構造だと思いませんか? なお、まかないくんはこの部分に、灰受け皿が付いております。
まかないくん解体新書2018③「キャスターが燃えない構造」
こんにちは!まかないくんです。 「炊き出し器なんてみたことないから、何が違うのか分からない」 という意見にお応えすべく設けました、この企画。 「まかないくん解体新書2018」 栄えある第三回のテーマは「キャスターが燃えない構造」 前回の記事ではキャスターが燃えない構造になるには以下の方法を試すことになりました。 1、ドラム缶の下をつける。 2、下にもう一層空気層を入れる。 3、さらにもう一層空気層を入れる。 なお、この実験は「薪」で行っています。(なぜ薪なのかは別の項で説明します) 1はこのような感じです。 何もないよりは熱が行かないのですが、それでもかなりの高温で、キャスター(ゴム車)のゴムの 表面の油分が飛んでしまっており、熱がかかっていました。 2はこのような感じで設置しました。 1よりもだいぶん熱は減りましたが、まだ熱が下に来ており、しばらくは大丈夫かもしれませんが 中長期で考えるとゴム車の劣化が懸念されました。 3はこのような感じに設置しました。 2と比べても格段に熱が抑えられ、キャスターの車輪まで熱が行っていないようでした。 それに合わせて、床への熱射が0となり、下の部分に熱がいかないカマドが完成しました。 2でも良いという意見もありましたが、 「炊き出し器は長期に渡って使用する可能性がある。だからこそ『より安全』な商品づくりを」 というヤマヤの理念として、三層構造でカマドを製造しています。 しかし、このカマド、このままだと使いづらいですね。 特に、「薪」を使う時この形では灰の処理が大変そうです。 そこで次の回では、