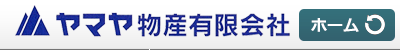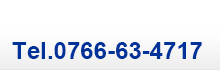⑤最初の炊き出し前の写真。 私は写真に写っているYMCA阿蘇の彼から多くのことを学んだ。特筆は衛生 …
トピックス
熊本地震の記録 その②
③今回の写真は実災害のために写真は必要最小限度にとどめた。写真はボランティアが芋掘りをしているところ …
熊本地震の記録 その①
熊本地震の記録 下記のものは私、山本が行ったものの記録です。災害は個々には違いがあって …
熊本地震炊き出し支援報告
熊本地震の際の 炊き出し支援報告をさせていただきます。 現在も「まかなくん」は熊本で活躍中です。 ・ …
避難所での気付き(足元暖房
常総市での使用から 避難所の暖房の技術的なことと気の付いたことをまとめてみました。 1、 エネルギ …

常総市の避難所で使用された足元暖房
9月10日に水害のあった 茨城県常総市の避難所で使用された 足元暖房について、代表の山本がまとめまし …

足元暖房について
足元暖房について 分かりやすくイラストでまとめました。 空気を汚さず 暖かさを保ちます …
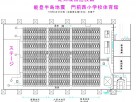
危機管理産業展にあたり
明日から 東京ビックサイトで 危機管理産業展2015年が開催されます。 当日 展示会場 …

危機管理産業展2015に出展します
ヤマヤ物産です。 10月14日(水)-16(金)に 東京ビックサイトで開催される 危機管理産業展20 …

今年も参加!KOCHI防災危機管理展2015!
昨日は甲信越、今日は四国。 どうも、まかないくんです。 今回は、これで3年連続参加にな …